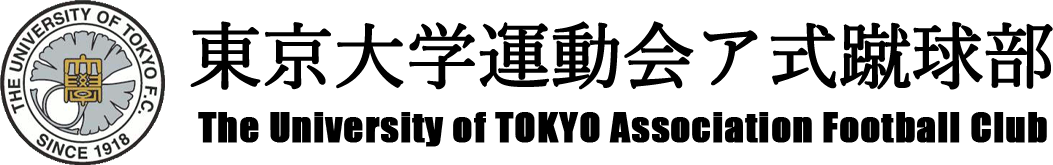Club Profile
東京大学ア式蹴球部は日本でもっとも歴史ある大学サッカー部です。
1918年、のちに大日本蹴球協会(現日本サッカー協会;JFA)創立に参画し同協会会長にも就任する野津謙が東京帝国大学ア式蹴球部を創設しました。1922年に早稲田大学、東京高等師範学校(現筑波大学)、東京商科大学(現一橋大学)とともに日本初のサッカーリーグとなる専門学校蹴球リーグ戦を開始させると、1925年に現在の関東大学サッカーリーグの前身となるア式蹴球東京カレッジリーグに参加、第1回大会では早稲田大学に次ぐ2位となるものの、第2回大会から前人未到の6連覇を達成しました。第5回ア式蹴球全国優勝大会(現天皇杯)では大学チームとして初めて決勝に進出するなど、まさに黄金期を創出しました。現日本代表のユニフォームが青いのは、当時多くの代表選手を輩出した東京帝大のユニフォームがライトブルーだったことに起因していると言われているほどです。
1956年に入れ替え戦に敗れて関東2部に降格し、また1977年に初めて東京都大学リーグに降格して以降、東京都大学サッカー連盟下での活動が続いています。
主なOBには野津謙(第4代日本サッカー協会会長)、竹腰重丸(元日本代表監督)、岡野俊一郎(第9代日本サッカー協会会長)などがいます。
大学サッカーの黎明とア式
サッカーというスポーツが広く普及している今の日本において、たいていどの大学にも「サッカー部」たるものは存在します。しかし、東京大学の「サッカー部」、通称「東京大学運動会ア式蹴球部」(以後、“東大ア式”と略す)の持つ歴史は、ほかの大学の「サッカー部」の歴史とは一味違います。
そもそも、“大学サッカー”という分野には、Jリーグよりもずっと深い歴史があります。というのも、日本で最初にサッカーをスポーツとして取り入れたのは、ほかでもない大学だからです。具体的には東京高等師範学校(今の筑波大学)が初めてサッカーを受け入れ、そこから他の学校にも広まり、卒業生らが日本各地でサッカーを普及させるなどの活動を経て、サッカーが我々の常識の一つに取り込まれるようになったのです。
東京帝国大学(今の東京大学)では1918年、当時の現役の生徒であり、後の日本代表にも選ばれた野津謙の手によって「東京帝国大学ア式蹴球部」が発足されました。これが東大ア式の始まりです。4年後の1922年には、東大ア式は当時の名門学校(今で言う早稲田大学や一橋大学、筑波大学)のサッカー部らとともに「専門学校蹴球リーグ戦」を創設します。日本で初めての公式のリーグ戦であり、大学のサッカーチーム同士で真剣に戦い互いに切磋琢磨することで、日本のサッカーの躍進に大きく貢献したのです。ちなみにリーグ戦の開催当初、東大ア式は圧倒的な強さを誇っていたと言われています。このように、発足当初の東大ア式は、大学サッカーだけでなく、日本サッカーの黎明期の中心的存在でもあったと言えるのです。
過去の戦績
野津謙の提案により1925年、一度の失敗を経て運営体系を立て直した新たなリーグ「ア式蹴球東京コレッジリーグ」が創設されることになりました。これが後の関東リーグです。東京帝国大学ア式蹴球部は、その第一回大会では2位になるものの、翌年のリーグ戦から6連覇を遂げるなど、リーグ戦開催当時はかなり強かったそうです。
しかし、サッカーが全国に普及するにつれ、華やかな歴史は徐々に過ぎ去ることとなります。
1956年、名称改め「東京大学ア式蹴球部」は関東1部リーグから2部リーグに降格。1977年には関東2部リーグから東京都1部リーグに降格しました。その後は主に都リーグの1部と2部の間を上下動することとなりました。
最近で言うと2009年。都リーグ2部から1部に昇格すると、その2年後の2011年には1部リーグでも優勝し、悲願の関東リーグまであと一歩のところまで迫りました。しかしその後は芳しい結果を残せていません。
今やJリーグや企業のクラブチーム、他の私立大学のサッカー部など、東大ア式より強いチームは全国にいくらでもあふれています。そんな現在からみれば、昔の記録は決して親近感のあるものではなく、今の私たちには「昔は強かったのだろう」と思いを巡らせることしかできません。しかし、こういった華やかな記録に気後れすることなく、一歩一歩、着実に積み上げて、東大ア式の新たな歴史の1ページを開くことが重要です。